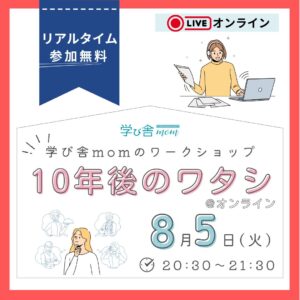登壇レポート:愛知県立大学大学「キャリア展望」講義

2025年6月13日(金)、愛知県立大学の幅広い学部からの学生を対象にした「キャリア展望」特別講義に登壇させていただきました。3、4年生を中心に約30名の学生が参加し、90分間にわたって代表矢上のこれまでの挑戦や失敗の軌跡、そして「キャリア=生き方」という視点を共有する時間となりました。
学生時代は、「挑戦のとき」。
冒頭に伝えたのは、「学生時代は“蓄える時”ではなく、“試していい時間”である」ということ。今この瞬間の選択にこそ、これからの人生のヒントが詰まっているというメッセージです。
講義の前半では、私自身のこれまでのキャリアと人生の紆余曲折──特に“失敗”や“選び直し”の経験を交えながら、こんな問いを投げかけました。
「あなたは、自分の人生の“ハンドル”を誰が握っていると思いますか?」
これは、講義を通して何度も立ち返ったキーフレーズです。たとえ正解のない時代でも、他人や時代に委ねるのではなく、自分で選ぶ感覚を持てるかどうか。その“主語の転換”こそが、これからのキャリアの軸になると私は考えています。

「何になりたいか」よりも「どんな人生を送りたいか」――DoingよりBeing、在り方を描いてみよう
就職活動が近づくと、私たちはつい「どんな職業に就くか」「何者になるか」に意識を向けがちです。しかし、変化の激しい時代には、肩書きや職業名以上に、「どんな人生を送りたいのか」という在り方(Being)が大切です。
どんなに素晴らしい企業に入社しても、「自分の価値観とズレた選択」だった場合、長く続けることは難しいでしょう。だからこそ、“Doing(何をするか)”の前に、“Being(どう在りたいか)”を見つめる必要があるのです。
この講義では、矢上自身の20代・30代の迷いや転職経験、そして創業に至るまでのプロセスを赤裸々に共有しながら、人生の「棚卸し」と「問いを立てる力」の大切さをお伝えしました。
AI時代に必要なのは「問いを立てる力」
AI技術の進化により、あらゆる分野で効率化が進んでいます。情報を検索し、正解を出すだけならAIの方が速くて正確です。
しかし、「どの情報を活かすか」「何を選ぶか」といった判断や意思決定には、人間にしかできない“問いの力”が必要です。
講義では、AIと共存するために必要なスキル=AIQ(AIとの協調知能)の概念にも触れました。
これからのキャリアは、単なる「情報処理能力」ではなく、
“人としてどう在りたいか”を描きながら選択していく力が求められます。
講義の後半では、「偶然を味方にする力」へ
後半では、矢上が何度も人生を立て直すうえで頼りにしてきた理論のひとつ、クランボルツ博士の「計画された偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」を紹介しました。
この理論は、「キャリアの80%は予期しない偶然によって決まる」と述べたもの。驚くかもしれませんが、計画よりも偶然こそが未来をつくる要素になるという視点です。
では、偶然を「チャンス」に変えられる人とは、どんな人か?
矢上はこう伝えました。
- 「迷っているときこそ、小さく動くこと」
- 「正解探しではなく、実験を繰り返すこと」
- 「他人の声に答えを委ねず、自分の違和感をスルーしないこと」
完璧を目指すのではなく、未完成な自分を実験台にしてでも、一歩踏み出してみる。それが“偶然”を味方にする第一歩になります。
学生から寄せられた感想より
「キャリアは単なる職業ではなく、人生そのものだという言葉が胸に刺さりました。失敗が意味を持つものだと考えたとき、これからの選択肢が増える気がしました」
「“母親のウェルビーイング”という視点は自分の中になく、新鮮でした。就活を控える今、失敗をどう意味づけるかという考え方にも救われました」
「“何になりたいか”より、“どう生きたいか”を考えることが大切だと気づけました。自分と向き合うことを始めたいです」
学生の皆さんからは、キャリアの概念に対する視野が広がった、との声を多数いただきました。真摯な感想、レポートをありがとうございました。
今日の学びを、明日につなげるために
講義の最後には、次の3つの行動を学生の皆さんにお伝えしました。
1. 自分の「問い」を持ち続けよう
環境や立場が変わっても、自分自身に問いを投げかけてみてください。
「私は、どんな人生を送りたいのか?」
2. 小さな“実験”を重ねよう
「動きながら考える」ことも大切です。やってみないと見えない世界があります。
3. 他者と対話しよう
問いは、一人で抱えるものではありません。話すことで、自分の考えが明確になることもあります。
最後に
「私のキャリアは、何か大きな夢から始まったわけではありません。むしろ“失敗”がきっかけでした。」
でも、諦めなかったからこそ、次のチャンスがやってきた。
未来は、“いま”の積み重ねでできています。
「失敗」とは、挑戦した証であり、未来への種です。
完璧な計画や正解がなくても、
「自分で選んだ人生を生きる」ことが、これからのキャリアの本質です。
AI時代のキャリアとは、「AIにできないこと」ではなく、
「自分にしかできない問いと物語を紡ぐこと」。
今日の講義が、そんな“自分らしい選択”への小さなきっかけとなっていたら嬉しいです。またどこかでお会いできる日を、心から楽しみにしています。
このたびの貴重な機会をくださったAAI起業部(愛知県立芸術大学×愛知県立大学=INNOVATION)の顧問でもある神谷先生、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。